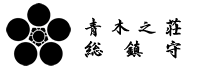神宮では昨年7月より内宮の宇治橋架け替えに向けての準備を進め、来る平成21年11月3日(文化の日)に完成し、当日行われる「宇治橋渡始式」終了後より、新しい宇治橋を渡橋できる予定となっております。
青木天満宮では、伊勢の神宮の宇治橋竣工を記念して、特別参拝旅行を企画いたしました。氏子総代の皆様お誘い合わせの上、多くの御参加を心よりお待ち申し上げております。
参加要項
●企画: 青木天満宮
●日程
11月3日 城島(14:00出発)?フェリー船中泊
11月4日 伊勢の神宮外宮・内宮参拝?二見浦「夫婦岩・二見興玉神社参拝」 ?宿泊ホテル16:30着予定
11月5日 8:30出発?世界遺産「平城宮跡」?東大寺?春日大社参拝?フェリー船中泊
11月6日 城島(11:00着予定)
●最小催行人員20名
●参 加 費 : お一人様 ¥66,000円
●服 装: : 伊勢の神宮参拝時は、男性:ネクタイ・背広着用 女性:それに見合ったもの
●申込み締切:平成21年9月末日まで
●詳しくは、〒830-0224城島町上青木950 青木天満宮宛
電話0942?62?4376 FAX 54?8988
 ホームページを開設しました。
ホームページを開設しました。
パソコン機器を扱うのは、大の苦手。なんとか時の流れに取り残さないよう、勉強を重ねてまいります。
どうぞよろしくお願いします。